観劇プログラム 第5回『ヒトラーを画家にする話』

観て話して、個々の演劇体験を深める場
演劇のクラス「新しい演劇のつくり方2022」では『三月の5日間』(チェルフィッチュ)を原作とし、生徒の皆さんが新たな物語の戯曲を書き、演出し、演じ、発表していく授業が進められ、先月幕を閉じました。同時に、GAKUでは、10代と演劇との出会いをもっと広げていきたいと考えています。そこで、同授業の総合ファシリテーターでもあり演劇ジャーナリストの徳永京子さんによる「観劇プログラム」を開催しました。
第5回目となる今回の観劇作品は徳永さんが企画コーディネーターを務める東京芸術劇場「eyes plus」選出劇団・タカハ劇団の最新作『ヒトラーを画家にする話』。トークゲストにはタカハ劇団主宰で脚本家、演出家、俳優の高羽彩さん、プロデューサーの半田桃子さんをお招きしながら、皆さんの本作品の感想や考察を交わし合いました。


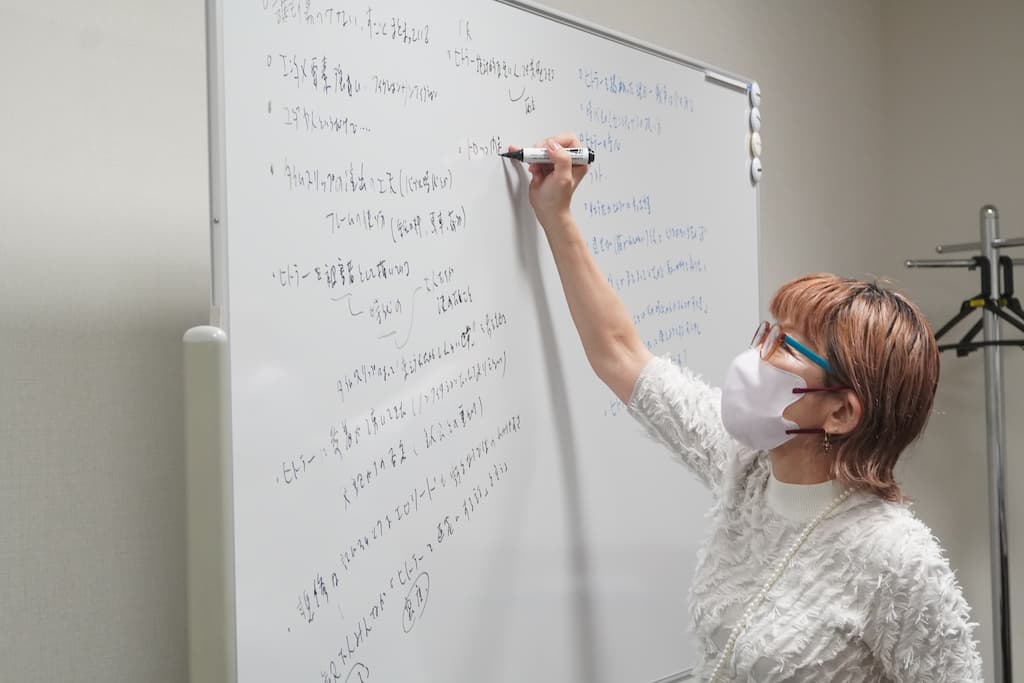
史実を演劇にするということ
「進路に悩む美大生、僚太、朝利、板垣」。登場人物の3人は「ひょんなことから、1908年のウィーンにタイムスリップしてしまう」。そこで彼らが出会ったのは「ウィーン美術アカデミーの受験を控えた青年、アドルフ・ヒトラー」。「彼らは未来を変えるため、ヒトラーの受験をサポートする」という物語の今作。以前、高校の先生から掛けられた「今の高校生はヒトラーとアウシュビッツ(強制収容所)の関連性がわからないかもしれない」という言葉が忘れられず、それが今作を制作するきっかけになったと言う高羽さん。言葉を絶する「人を人とも思わないような行為」が繰り返し行われた「ホロコースト」。それに私たちがどのように向き合っていけばいいのか、そもそもその史実を忘れないためにはどうしたらよいのか。
「ヒトラーが僕たちと変わらない一人の人間として描かれていた。ヒトラーも僕たちのようになり得たかもしれないし、僕たちもヒトラーのようになり得るかもしれない」「登場人物の動きや照明等の演出が、とても象徴的なものとして感じられた。とはいえ、それが何を表しているのかという答えが明確にあるわけではないから、考えさせられた」と生徒の皆さんは、観劇を通した迫ってきた気持ちを少しずつ言葉にしていきます。


つくり手としての葛藤
通常の登場人物と同じような愛着をヒトラーに寄せてしまうような作品にしてはいけない。同時に、「ヒトラーは狂人だった」だけで終わらせていいことではない。ヒトラーを作中に登場させるということに、大きな葛藤があったと言う高羽さん。つくり手としての倫理観と生徒のみなさんの素直な感想が交差しながら、ディスカッションは進んでいきます。
「今作はとにかく若い人に見てほしいと思ってつくりました。今回10人以上の登場人物がいるのはヒトラーという存在を様々な視点で見るため。葛藤した分だけ登場人物がどんどん増えていったんです」と胸の内を明かしながら、生徒の皆さんと言葉を交わしてくださいました。

10代と演劇の出会いを豊かに
2023年3月にはじまった「観劇プログラム」は、今回で5回目。これからも演劇と10代の出会いを豊かにしていきたいという想いで、様々な企画を立ち上げていく予定ですので、是非ご期待ください。

